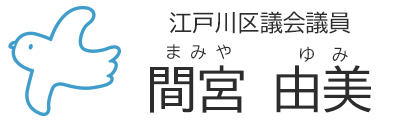福岡労働局とともに、障害者雇用に取り組んでいる会社「丸福水産」さんにうかがいました。
法定雇用率の達成という義務的な側面だけでなく、障害者を企業の「戦力」ととらえ、慢性的な人手不足に悩む工場などの業界の再生と成長を達成した具体的な事例です。
福祉事業所での「学び」から、一般企業での「就業」までを一貫して支援する独自のモデル。その成功の鍵の一つは、「業務の細分化」。
売上150%増、残業大幅削減、労災・クレーム減少といった劇的な成果を上げた事例を交えながら、障害者雇用の成功のこのモデルが、日本全国の人手不足の解決策と、障害者自身の雇用を増やすことになり得る可能性の示唆がありました。
「丸福水産」では、熟練の切り身職人が、原料搬入から加工、箱詰め、運搬まで全ての作業を一人で行っていたため、手を切る、数の間違い、クレーム多発など非効率で事故も多発していたとのこと。
しかし、障害者雇用を進めたことで、職人は「魚を切る」というコア業務に専念。周辺業務(清掃作業を含む)を障害を持つ従業員が担当することで、職人の負担が減り、生産性、品質、安全性が向上した、とのことです。
そしてそこには、障害者それぞれへの手厚いサポート体制がありました。
例えば、利用者の困りごとを定期的にヒアリングし、丸福水産と共有する。共有された内容は、iPadで閲覧できる写真付きの作業マニュアル作成に活かされ、利用者の不安を軽減する。月に1回、丸福水産と福祉施設の責任者間でミーティングを実施し、利用者の状況共有や職場環境の調整をメッセージツールも活用して行っている、などです。
また、正社員への移行プロセスもあり、社会的使命と事業継続性の両立が、今後の重要な課題として挙げられていました。
そして、それらを支援しているのが、「福岡モデル」と言われる雇用に向けた助成金の制度とそれを実現に向けようとしている労働局の皆さんの力です。
ともにつくり上げる姿勢があるかどうか、ここが障害者雇用を進めるための必要な点だと確信しました。
(視察④ 8/7 福岡・丸福水産における障害者雇用のとりくみ)