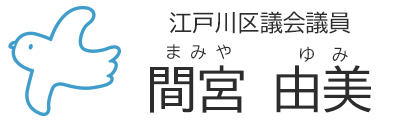| 会議 | 令和7年 7月 福祉健康委員会-07月09日-03号 |
|---|---|
| 日付 | 令和7年7月9日(水) |
| 開会 | 午前10時00分 |
| 閉会 | 午後0時14分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 発議案審査 第5号・第6号…継続 第5号:江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第6号:江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例 2 陳情審査 第49号の3・第51号・第53号・第65号…継続 第49号の3:区政等に関する陳情 第51号:マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情 第53号:自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情 第65号:江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情 第71号:電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情 第72号:「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情 第75号の2:『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情 第78号の2:魅力的な江戸川区にするための陳情 3 所管事務調査…継続 4 執行部報告 (1)令和6年度江戸川区の高齢者虐待対応状況について (2)令和6年度江戸川区の障害者虐待対応状況について (3)Edogawa Beer Project推進パートナー事業者の決定について (4)夏の祭典2025について (5)区内小児科の状況について (6)健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて (7)ゲートキーパー養成講座について 5 その他 |
【第51号:マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 マイナ保険証については、解除申請は平均月に30件程度あるということ。そして、新規に登録をされる方は、月平均680件程度ということで、前回の委員会の中でお聞きをしたところです。今、解除理由については、今、課長からお答えがありましたが、その解除理由を聞きますと、マイナ保険証そのものの課題というのが浮き彫りになるような理由ではないかなというふうに思いました。先ほどの件数なのですけれども、この件数については解除件数、あるいは新規に登録をされる件数、これは特に変動は、その後はございませんでしょうか。
◎加藤広司 医療保険年金課長 大きく変動は特にありません。
◆間宮由美 委員 もう一点お聞きをしたいと思います。
失効した紙の保険証を持ってきたとしても、医療現場としては、今までの負担割合で受診できるようにすることを容認するという方針を厚生労働省が固めた、そういった報道が出ています。これについては、具体的には江戸川区としてもどのような対応になっていくのかということをお聞かせいただけますか。
◎加藤広司 医療保険年金課長 今、間宮委員のご質問の件につきましては、後ほど資料で説明をさせていただく予定ではございますが、国のほうから6月30日に通知がございまして、国民健康保険証の有効期限が切れた以後、期限切れの健康保険証などを提示した場合における医療機関等の対応についての通知となります。江戸川区の国民健康保険証は9月末に有効期限が到来しますが、通知はこの期限が到来した以後、提示した場合の対応で、令和8年3月末までの間の対応についてお知らせしています。こちらにつきましては医療機関などがオンライン資格確認などをして、国民健康保険の資格が継続しているということを確認ができれば、そのまま保険診療ができるというようなものでございます。
◆間宮由美 委員 そうしますと、その期限切れの保険証、失効した紙の保険証を持ってきたとしても、医療機関の中でオンライン確認をして、そして確認が取れれば、そのまま今の持っている保険証と同じ割合で医療が受けられるということで、よろしいわけですね。それで、そうしますと、医療機関への周知が必要になってくるかと思います。オンライン確認ができたらばということなのですけれども、オンライン確認ができないような医療機関というのは、区内にはないのでしょうか。
◎加藤広司 医療保険年金課長 基本的には、病院のほうが建て直しだとか何か工事だとか特別な事情がなければ、基本的には、オンライン資格確認をすることができる状況になっていると認識しております。
◆間宮由美 委員 そうしますと、医療機関での周知がやはり必要かと思いますので、そちらはどうぞよろしくお願いいたします。
また、江戸川区としては、7月に全ての人に資格確認書を送ってくださることになっていると思います。その期限が来年の7月までとのことだと思いますので、また1年経てばマイナ保険証との関係でもいろいろ変わってくることがあるのかなと思うところですけれども、まずは今現在は皆さんに安心してくださいと伝えることができる内容かと思っております。
—
【第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 民間子育てひろばへの15年間の補助金の在り方などにつきましては、前回の委員会の質疑で理解をいたしました。陳情書には、令和5年度以降、23区でも子育てひろばに関する要綱の改正、また補助額の増額がされている区が出てきているということが書かれています。令和7年度になって、国としても賃借料加算が新たにできたり、またあるいは若干の補助額の増額があるというふうにも聞いています。それらを受けまして、区としての検討もされているのではないかと思われるのですが、どのように検討が始まっているか、お聞かせいただきたいと思います。
◎佐藤英 子育て支援課長 現在、当該団体から提出されました報告書による勤務実態などを精査させていただいているところでございます。また、他区で改正された状況、他区での補助額などにつきまして、これから今後調査させていただく予定としております。
◆間宮由美 委員 では、国としても若干の増額などについて変わってきているということも含めて、他区での調査などもしながら検討を始めていってくださるということが分かりましたので、検討状況については適宜お伝えいただければと思います。
—
【執行部報告について】
◆間宮由美 委員 まず、虐待対応状況についてお聞きをします。施設職員による虐待が増えているとのご報告がございました。実は、先日も知的障害の方で、親御さんがいないに等しい方なのですが、その方が小さいときに暮らしていた家庭寮で数百万円の貯金を寮母さんと一緒に貯めていた。ところが、次のホームに行ったときに、これがなくなっているということが分かったということでしたので、まず、ご相談に行こうと思っていたところでございました。経済的虐待というのは知的障害の方ですとか、あるいは認知症の方へのものなどが多いのかなとも思うところなのですが、その他の虐待についても含めて、虐待と認定されたときに、その後の対応がどのようにされているかということ。先ほど、助言・指導というご報告もございましたが、もう少し具体的に施設への対応についてお聞きをしたいと思います。
◎山野辺健 介護保険課長 まず、介護のほうの施設の虐待についてでございます。施設の虐待につきましては通報がございましたらば、そこにつきましては担当の係のほうで施設のほうに行きまして、職員とそれから、周りの職員、そういったところで状況確認をいたしまして、状況によって虐待ということで認定をさせていただくというような流れでございます。原因といたしましては、やはり今ちょっと職員の方も少なくなっていて負担が増えているというようなところのストレスからついというような話も別に聞き取りをすると、そういう話もございます。そういったところでその環境の改善ですとかそういったところについては介護保険課として進めていきたいというふうに考えているところでございます。
◎上坂かおり 障害者福祉課長 障害者に関しましては、施設職員による虐待に関しては、当然、助言・指導だけというよりは、そこでまず必ず改善報告書というのを出していただくように施設のほうにはお願いをしています。その改善報告書が虐待案件に対して対応しているかどうか、そこが実効性のあるものかどうかというのを確認して何度かやり取りをした上で、そこで可能ということであれば、改めてその報告書も含め、東京都にも報告をさせていただくというような形で対応させていただいております。
◆間宮由美 委員 多分、介護保険のほうでも、今の障害者のほうで言われたように細かなもう少し細かなこともきっとされているのだと思うのです。ただ、原因のところで負担が増えているからストレスからついって、ついってとんでもないことだと思うのですよね。虐待もそうですし、ハラスメントもそうですけれども、受けた傷がずっと残ります。障害の持つ方への、また高齢者の方への虐待が家庭内でももちろんなのですけれども、施設でなどあってはならないと思いますので、やはりキャッチする力も研ぎ澄ましていただきながら、虐待ゼロの施設というのをするために、指導援助をこれからもお願いしたいと思っています。
続きまして、先ほど小児科のことについてのご報告があったのですが、委員長、そちらも続けてよろしいですか。
○中道貴 委員長 どうぞ。
◆間宮由美 委員 区東部医療圏についても話がありました。区東部医療圏自体に病院自体が少ないということも言われていますが、小児科もまた少ないというのも今のご報告で分かりました。厚生労働省の令和5年の調査の中では、全国の小児科のクリニックというのが、1万7,778施設あったと聞いています。1984年というところと比べると、2万9,164施設ということで、そのときから比べて39%減少していると厚生労働省は出しています。前回の委員会でお伝えをしたお母さんというのは、2人の病弱なお子さんを抱えています。だから、1人の子が遠くの病院の入院になったときに、その下の子は病院には連れて行かれないということがほとんどですので、とてもご苦労されております。先ほど、臨海病院としても頑張ってくださっているが、とのことだったのですけれども、他の病院も含めて江戸川区内で入院できるように江戸川区内でも子どもが入院できるようにと考えたときに、区としては何かできる支援というのはありますでしょうか。
◎岡田久仁子 健康推進課長 区として具体的にできる支援というのはちょっと今、思いはつかないのですけれども、そういった区内で小児救急が回っていくような体制を整備していくということを課題として医師会等とも課題共有をしていこうとは思っております。
◆間宮由美 委員 ぜひ、お願いいたします。小児科の減少につきましては、少子化が進んでしまって、患者数も減少しているということも影響しているとは言われていますが、そもそもその小児科の診療報酬が安くて経営を維持できないということも問題があると言われています。ですから、少子化に歯止めをかけるというのであったとしたならば、安心してかかることのできる小児科が近くにあるということは大切なことだと考えますので、ぜひ今後、全国市長会などへの要望などとしても区からこの診療報酬を上げることなども要望していただきたいと考えるものです。よろしくお願いいたします。
—
【その他について】
◆間宮由美 委員 生活保護に関して2点お聞きをします。2点とも報道があったばかりなので、こちらでお聞かせいただければと考えています。
1点は、国が生活保護費の基準額を引き下げたことに対して、最高裁で違法とされたと報道がございました。このことについて、区としては今後どのように対応していくことになるかということについてお聞かせください。
◎安田健二 生活援護第三課長 今、委員がおっしゃいました、生活保護基準額を引き下げたのは違法だということで、最高裁判決が先日、違法というふうに判断されたところです。この判断をもとに、恐らく全国の一連の訴訟が、これ統一判断として影響してくるということはもう明らかだということで、原告側の主張を認める形で終結に向かうというふうには考えられております。その際、厚生労働大臣も、適切に対応するというような判断を示されておりまして、我々としましても、今後、例えばそれが減額相当分を支給するのかとか、そういったことも含めて、国の判断を注視していきたいと、そういうふうに考えているところでございます。
◆間宮由美 委員 地裁高裁では違法適法と判断が分かれたけれども、最高裁では、生活保護の基準額の引下げを初めて違法と認めた統一判断が示されたということだと思います。最高裁判決では、この国の基準額引下げについて、専門的知見との整合性を欠いて、国の判断過程や手続きには過誤欠落があった。厳しく指摘があったということは憲法25条にある、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための生活保護制度、これに対する国の明確な判断として重要な判決であったと思うところです。2013年から15年に引き下げられた基準額について、約1,000人の方が訴訟を起こしていて、減額された保護費は3年間で約670億円に上るとございました。江戸川区内で、そのときに受けていた人が何らかの訴えをした場合、あるいはしなかったとしても、先ほど課長がお話いただいたように、減額相当分を支給するのかどうかなどについて、何らかの措置がとられるとしたら、これはまた大変な額になる、大変なことになるのだと思われますので、お聞かせいただいたところです。国の動向を見てということですので、方向が決まりましたらば、またご報告を願いたいと思います。
もう一点は、先ほどの虐待にも通じる話ともなるのですけれども、末期がんである方が既に3年間、部屋からも自由に出られずに、来てもいない訪問看護を受けたことになりながら、そのホームから出られずにいるという報道がありました。そして、その記事の中で、訪問看護で不正、過剰な診療報酬を請求している会社が運営している北関東のホームに江戸川区からの入所が大変多くて、3年間で200人と書かれていました。また、この件についての取材を受けた担当課長からは、そのような情報、これはこの情報というのは200人いるというのは知っているのだけれども、不正受給の件、この件については把握していないので、現時点で調査することは考えていないとお答えになっているということも書かれていました。そうしますと、把握していないので調査は考えていないということは、把握はその後されたのだろうかと気になるところでございますし、ニュースになってしまっているために、きちんとした事実を知りたいと考えます。詳細をお聞かせいただければと思います。
◎安田健二 生活援護第三課長 この件に関しましては、我々もSNS等拝見させていただきまして、まずは現状入っている方、今、委員がおっしゃったの200人とおっしゃっていますけれども、これは3年間で入所されている方の累計でありまして、我々としては今、把握しているのはその対応している施設については64件であります。そこについて、訪問看護、訪問介護等のレセプト等を確認させていただいて、過剰なものになっていないかということを確認しているところであります。その結果としましては、確かに金額として高額なところもありますけれども、人によっては、かなり低額の部分もありまして、それが高いか安いかという判断については、なかなか難しいところがあります。そもそも、そういった地方の施設に入所させる、していただくといった場合には、我々としては、そのケアマネさんとか計画相談員、そういった関係機関からその居宅での自立した生活が困難である、いわゆるその寝たきりであるとか重介護者、そういった方々を中心に対応させていただいておりますので、軽度な方がそういったところに入るということはまず考えておりません。ですから、ホームページにありますように、末期がんで3年間その場所にいるという状況が、ちょっと考えられない状況でありまして、記者に確認をしたところ、それは江戸川区の方ではないということは把握はしているのですけれども、だから、そういった重介護等が必要な方に対して、果たして適正な介護がどうなのかというところについては、我々としても、しっかり見ていかなければいけないなと思っております。
◆間宮由美 委員 レセプトについても確認をしてくださっているということで、その中では特に問題があるような方は見受けられないというふうなお話なんだと思います。ただ、記事に出ているような末期がんで3年間いるなんて考えられないと今おっしゃったのですけれども、その考えられないようなことが起きている施設であるということだとしたらば、やはりもう少し踏み込んで見ていっていただかないといけないのではないかなというふうにも思うところです。ただ、ニュースになっていることが事実と違うのであれば、違うということも含めてきちんとお伝えをしたいと思いますので、事実経過をお聞かせいただいた次第です。課長がおっしゃってくださったことはよく分かりました。