| 会議 | 令和7年 3月 福祉健康委員会-03月13日-13号 |
|---|---|
| 日付 | 令和7年3月13日(木) |
| 開会 | 午前10時00分 |
| 閉会 | 午前11時44分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 議案審査 第6号・第7号・第23号~第29号 第40号~第47号…可決(全会一致) 第 6 号議案 令和6年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号) 第 7 号議案 令和6年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) 第23号議案 江戸川区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 第24号議案 江戸川区育成室条例の一部を改正する条例 第25号議案 江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第26号議案 江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第27号議案 江戸川区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 第28号議案 江戸川区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第29号議案 江戸川区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 第40号議案 債権の放棄について 第41号議案 債権の放棄について 第42号議案 債権の放棄について 第43号議案 債権の放棄について 第44号議案 債権の放棄について 第45号議案 債権の放棄について 第46号議案 債権の放棄について 第47号議案 債権の放棄について 2 発議案審査 第5号・第6号…継続 第5号:江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第6号:江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例 3 請願・陳情審査 第31号…不採択(2:6) 第32号…結論に至らず、審査未了 第37号・第49号の3・第51号・第53号・第65号…継続 第31号:江戸川区の生活保護行政における生活保護受給者の著しいプライバシー侵害といえる江戸川区独自書式の生活状況報告書に関する陳情 第32号:パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る意見書を国に提出することを求める請願 第37号:接種台帳の保存期間延長に関する陳情 第49号の3:区政等に関する陳情 第51号:マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情 第53号:自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情 第65号:江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情 4 所管事務調査…継続 5 執行部報告 (1)特別養護老人ホーム(共生型の複合施設)の開設について (2)生活保護利用者・くらしごと相談室利用者へのアンケートの実施について (3)自治体システムの標準化について (4)快適睡眠フェア2025 6 その他 |
【第6号議案、令和6年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)について】【歳入、第1款国民健康保険料より審査】
◆間宮由美 委員 この度の保険料の改定につきましては、コロナ禍が過ぎてから所得が増えたということで、保険料が多く集まったということと、被保険者が少なくならなかった。そういった二つの理由の中で、法定外繰入を返すことができるくらいの収入が出たと。この度、約7億6,000万円が要らなくなった、繰り入れなくてもよくなったとお聞きをしています。そうしますと、今後ですけれども、区民の所得が増えるということで、保険料もまた安く抑えていくことができるというふうに考えてよいのでしょうか。
◎加藤広司 医療保険課長 被保険者の所得が上がりますと、保険料が下がる効果が生じます。ただ、医療費の伸びのほうと勘案して実際に下がるかどうかは、それとの総合的な乗率計算となります。
◆間宮由美 委員 低く抑えられるということ自体については賛同するものです。また、所得が上がっているという感覚というのはあまりないという人が多い中ではあるのですけれども、この度、ここに保険料のところでこのように出てきているということは、これはこれでとてもよかったなと思っています。病気にならないことが、医療費自体の抑制につながると思いますので、そこにこそ力を使っていくことが今後必要になってくるかなと思うところです。この予算については賛同いたします。
—
【第24号議案、江戸川区育成室条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 今ほど児童発達支援センターの中身についての討論があったところでございます。発達支援センターができることで、二つの育成室がなくなるということになります。これまで小岩のほうは児童発達支援センターのほうに行くことができるのですけれども、これまで臨海育成室のほうですね、もう一つの。こちらに通っていた子どもたち、これは何人だったのか。その子たちはこれからどのようになるかということ、また臨海育成室で勤めていた方々、この方々はどのようになるかということ、さらに臨海育成室の場所は、今後何かで使うことはお考えかということ、この三つをお聞かせください。
◎木村秋生 保育課長 まず、1点目でございます。今、臨海育成室のほうには38名のお子さんが在籍をしております。閉室後どうなるかというところに関しましては、葛西のほうに児童発達支援センターがございますので、保護者の方のご希望があれば移行という形で予定をしております。
2点目、職員につきましては、先ほどのお話もありましたけれども、正規職員に関しましては異動、会計年度任用職員、専門職につきましては、センター化になったというところで、その事業者さんのほうからのお声がけでというところでもありますし、また保育課のほうでも、どういうような形で今後考えているかということの意向の確認も併せてしていきたいと考えております。
3点目でございますけれども、今後の検討というふうな形で考えさせていただいています。
◆間宮由美 委員 そうしますと、葛西臨海育成室はもう少し少ないと思っていましたが、38名ということでよろしいですね。葛西育成室、現在は何人ぐらい今いるでしょうか。
◎上坂かおり 障害者福祉課長 定員は40名という形にはなりますが、40名が毎日来ているわけではないので、曜日等を調整させていただいて通所できるような形にさせていただきたいと考えています。
◆間宮由美 委員 臨海にいた子たち38名が定員40名のところに行く、葛西育成室ももう今いっぱいだと思うのです。そのときに曜日を今考えてということだったのですけれども、必要な曜日が削られるようなことというのがないように、ぜひお考えをいただきたいというふうに思っています。育成室から発達支援センターとして、バージョンアップしていく。これはここには敬意を表しますし、ここについても賛同いたします。
—
【第25号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 この条例につきましては、4点の改正が行われるということでお聞きをしています。国保料の料率の改正、そして二つ目が、賦課限度額の引き上げ、そして3点目に均等割の軽減基準の改正、そして4点目に7割、5割、2割の均等割の軽減と未就学児の半額軽減の額を引下げ。どれも区民にとっては多くの引下げの効果があるということでございます。特に、2点目の賦課限度額の引上げ、これにつきましては、これまでは所得が1,000万円でも1億円でも同じ限度額だった。これを変えていこうということで、具体的にはこのたびは高所得者への引上げにはなるけれども、しかし中間所得者層およそ400万から800万円の方への額が、見直されるということをお聞きしています。ですので、この4点はどれも歓迎をするものになります。国民・区民にとって負担が減っていくという形になりますから、ありがたい改正となるのですけれども、これらはなぜ改正できるのかということをお聞かせください。
◎加藤広司 医療保険課長 賦課限度額の引上げにつきましては、国民健康保険法施行令で改正が行われているものでございます。こちらについては国は、賦課限度額を超える世帯数が全国平均1.5%以内に収まるように管理をされておりまして、今回、国では令和7年度は全国平均で1.59%を超えると判断をして、改正に至ったものでございます。
◆間宮由美 委員 1.5が1.59になるということで国のほうでの改正ということで分かりました。これについては、賛同するものでございます。
—
【第28号議案、江戸川区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 これにつきましては、文字だけ、ロをハに、という変更かと思ったのですけれども、よくよく聞きますと、ここには介護保険の施行規則が変わったということで、大きく2点が変更となっているようです。この内容について、まずご説明ください。
◎山野辺健介 護保険課長 この二つの改正でございますけれども、一つは社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャー、熟年相談室についてはこの3人のこの三つの職種を、1名ずつ配置をしなければならないのですけれども、ここを市区町村の判断で地域の実情に応じて、複数圏域で合算して配置することを新たに可能としたものということでございます。これ本区でいいますと、今は18か所、熟年相談室がございますので、区全体で見たときに、18人のその社会福祉士の方と保健師の方と、あと主任ケアマネージャーの方が配置されていれば、熟年相談室によっては多い少ないという違いがあったとしても、より効果的な事業実施を行うために、このように柔軟に配置するということは構わないということになるということでございます。ただ、やはりその少ないところというのはやはり業務負担も増えてしまうとか、いろいろ課題が出てくると思います。そういったことでその区民が支障がないようにお互いその相互支援ですとか、情報共有を行ったりですとか、そういった具体的な手法は検討することということになっているところでございます。これが一つでございまして、あともう一つは3職種の方、これが常勤でなければならなかったのが、その常勤に換算をして1人分となれば配置が可能になったということでございます。これは例えば非常勤の方、2名の方が、曜日を分けて勤務をして、それで今までどおりの1人分となった場合については、常勤とみなすということが認められるようになったということでございまして、これは採用の幅が広がるということで期待をしているところでございます。
◆間宮由美 委員 これは大きな改正になると思います。ただ、それぞれ違う事業所の中でどのように人数を合わせていくかということが課題になってくると思います。そこについては区が間に入ってくださるということになるのでしょうか。どのようにお考えか、そこをお聞かせいただけますか。
◎山野辺健介 護保険課長 そこについては、このように可能となったということなのですけれども、ここについては、熟年相談室の運営協議会で意見を聞いて、必要と認められる場合に実施が可能となるというものでございます。なので、先ほど申し上げたとおり、まずその効果的な事業実施が行えるということが考えられること、それから、その区民に支障がないように支援、情報共有を具体的な手法を検討することということがあります。そういったことの意見を踏まえて、あとその現場の意見を聞きながら進めていくということになるかなというふうに思っているところでございます。
◆間宮由美 委員 熟年相談室などの運営協議会、そしてまた皆さんからのそこの中での意見などを聞きながらということなので、そこをうまく間に入りながらまとめていっていただければと思うところです。介護事業所の皆さんからお聞きするのは、毎日のように事業所の閉鎖とか事業の譲渡、こういった話がいろいろなところから入ってくるという中で、熟年相談室だけでなくて、ケアマネ事業所ですとか、福祉養護事業所なんかもサテライトなども認めてもらいたいくらいだという声も聞かれています。今、人手不足と言われる中で、辞めていく人も多くいる。この中で、でも熟年相談室を存続するためには、これは一つの非常に大事な方法となると思います。ただ、先ほどの心配部分、他の事業所がいくつもある中での合わせていくということですから、この条例の改正が本当に現実的に包括支援センターの充実となるように期待をしているところです。よろしくお願いいたします。
—
【第40号から第47号までの各議案について】
◆間宮由美 委員 第40号から第47号は、破産法の中で免責許可が出たということで、債権放棄が行われようとしているものだと思います。債権放棄するものは生活保護費返還金となっています。金額を見ますと、十数万円からですが、一番多い方は約196万円となっています。返還金の額がなぜここまで高額になっているのかということについてお聞かせください。
◎髙橋徹成 生活援護管理課長 ただいま例として挙げていただきました、196万円の返還金につきましては、生命保険の解約金を現金化したということにつきまして、その金額についての返還を求めるものでございます。
◆間宮由美 委員 この方の場合は生命保険の解約金ということで、これは普通というか、今、生活保護を受ける場合には、受ける前に解約をしてもらって、そして、それをきちんと自分のお金として使ってもらってお金がなくなった時点で生活保護を受けるというふうになっているかと思うのですけれども、この方の場合は、それはされなかったというのは、どうしてだったのでしょうか。
◎髙橋徹成 生活援護管理課長 この方の場合、ちょっと特異なケースでございまして、ご本人が認知症を持っていたためにご自身で申請ができずに、そのときはこの保有したまま解約の処理ができないままに保護を開始したのですけれども、その後に後見人がつきまして、後見人によって申請されたため、その時点で解約した一つになっております。
◆間宮由美 委員 特別なケースということで承知をいたしました。返還金が生じるといったとき、このように破産をするということが生活保護を受けていてもできるということではあるものの、この返還金については今のようにこの第40号から第47号の方々のように、返還金があると言ったときに嘘をついてちゃんと報告をしていなくて、それが後で分かって返還をしてもらうという場合もあるけれども、今回のこの第40号から第47号の方々は、それとはまた別の形でのことになっているということで、事前にお聞きをしました。ですので、仕方がないということなのだとは思います。ただ、そうは言っても、なるべく債権の放棄ということがなく済むように、事前に聞き取りなどもしっかりとしていくことというのがこれからまた求められているのかなと思います。これからもよろしくお願いいたします。
—
【第31号、江戸川区の生活保護行政における生活保護受給者の著しいプライバシー侵害といえる、江戸川区独自書式の生活状況報告書に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 記書きにあるように、江戸川区独自書式である生活状況報告書の廃止とあり、これについては委員会の中でお話をしてきたように既に廃止をしているような状態である別のものに変わっているということですので、私たちは採択としたいと思います。
—
【第32号、パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に関わる意見書を国に提出することを求める請願について】
◆間宮由美 委員 付託されたものについて結論を出すということは、責務だと思っておりますので、結論を出したいと思っております。
◆間宮由美 委員 結論が出ないということは残念なことだと思います。
本日、もうこれで終了ということなので、意見だけ申し上げたいと思うのですけれども。パンデミック協定の交渉文書の改定素案、これが3月の8日の午後に世界保健機関加盟国に届けられたと伺っています。日本のWHO協会によりますと、誤った情報を正確にするための文書の改定ですとか、また最も意見が対立する箇所についての文書の改定があったということです。誤った情報というところでは、パンデミック協会がWHOの権力掌握であり、世界保健機関がとりわけ世界的なロックダウンを課すことを可能にするということ、これは誤った情報であるとして、ここについては国連憲章及び国際法の一般原則に従って自国の管轄内で法律を採択し、立法し、実施する国家の主権的権利及び自国の生物資源に対する主権的権利にも明示的に言及しているというふうになっている、変わったというふうになっているようです。また、最も意見が対立する箇所としての病原体へのアクセスと利益配分、こういったことについても文書が変更されていると思います。各国からの意見が出ることによって、草案が改定されていくということになっていると思います。それで、ここの記書きに書かれていますように、原文にはいろいろな不安な心配なことが書かれていますが、これについて記書きでは分かりやすく内容について、パンデミック条約の草案などについて国民に周知するということ、また議員や有権者その他一般国民から意見を聴取する手続きを開始することということで、2番目は少し難しいとかどうするかなとは思うのですけれども、しかし大事なことについて国民に知らせるということ自体は賛同できるものだなと思っております。
—
【特別養護老人ホーム(共生型の複合施設)の開設について】
◆間宮由美 委員 特養ホームのいずみさんについての件でございます。オープンするということで、各所から喜びの声をお聞きしています。実はちょうど昨日も、病院のMSWさんから入院患者さんの施設を探したいというふうにご相談があったのです。そこでケアマネさんとお話していたときに、このいずみさんのことをお聞きをしました。この中で共生型の複合施設ということで非常に期待をしているところなのですが、特筆すべきは施設の中の4階に防災拠点型地域交流スペースというのを設けているということかと思うのです。通常時は地域に開放するということで、町会やカルチャークラブ、そして介護教室とか医療セミナーなど学びの場としても活用していくということです。さらに定期的に子ども食堂の開催も予定していると聞いています。さらに、災害時には避難スペースとして機能させるということで、この施設はこの厨房とか事務室なども4階に配置しているということなので、食事の提供とか指揮命令系統も途切れることなく行えるというふうな施設になっているということです。これは先日、予算特別委員会でも申しましたが、新しい施設ができるときには区と防災協定を結んで、ぜひ地域の方が避難できるような場所にと申したのですけれども、このような施設が新しくできてくるということはとても大事なことと思っています。お聞きをしたいことは、この4階を災害時においては、地域の人々へ開放するということなのですけれども、水害時のときにはこの施設に暮らしている1階2階3階にいる方々は、どのようにされるとお聞きになっているかということをお聞きしたいと思いました。
◎白木雅博 福祉推進課長 今のところまだ開設前ということで、どこまで入所者と、それから地域の方々をどういう形でやるかというところまでの具体の詰めはまだできてございませんので、今後いよいよ建物が今月で引き渡されるというふうに聞いてございますので、法人のほうとその辺を詰めていければなというふうに考えておるところでございます。
◆間宮由美 委員 水害がもしすぐにあったときには、もう本当に皆さん押し寄せてしまうんだと思うのです。ですから、今いる方との関係としてどうするかというのを具体的に、ぜひ一緒に考えて差し上げたらと思っております。「中サービス-中負担」の中で、特養ホームなども見直しの対象となっていたかと思ったのですけれども、今後は、特養ホーム全体としてはどのようにされていく方向でしょうか。
◎白木雅博 福祉推進課長 今回の見直しの中、及び、それから今回、今期の介護保険計画の中でもお話させていただいてございますが、中長期的には、今回のこのいずみさん、それから、もう1施設、1年後にさらに開設の予定の特別養護老人ホームを今建設中でございますが、そこまでできた段階では、中長期的にある程度その緊急の待機者の方の取扱い解消は見込めるという予想を立ててございますので、新規の特養建設については、中長期的には今のところ、江戸川区としては需要がないであろうというふうに想定をしているところでございます。
◆間宮由美 委員 もう一つが1年後にできるということで、待機の方々のその解消が見込めるというふうに踏んでおられるということですので、そこのところは見誤らないように都度、本当に今、どうされているかということをぜひ検討しながら、そこについては新しくつくる、つくらないについてを進めていただきたいと思うところでございます。この施設につきましては、普段の日も、いざというときも心強い存在だというふうにご自身たちが書かれていますが、このような施設が地域にできることに感謝をしております。
—
【不適切保育の件について】
◆間宮由美 委員 不適切保育の件でお聞きをします。人は変わることができるって確かにそう思います。しかし、子どもに対して行われたことについては、ここは厳しく見る必要があるのではないかと考えるところです。今回の保育士については、2年前に指導していて、改善をしていたと予特でのお話がありましたが、私はお聞きをしながら、改善ということに疑問を持ちました。話し方とか考え方というのはすぐに変わるものではないと思うのです。厳しい言い方ですが、第三者の前ではきちんとできる、でも誰も見てないところでは自分が思うように振る舞うということがあると考えるべきではないかなと思うのです。お聞きしたいことは、まず不適切と言われること、ひどい言葉を使うとか、子どもの心に傷をつけるということを、なぜその保育士がしたのかということです。例えば、それが悪いことと思ってはいなかったからなのか、それとも悪いとは思っているけれども、自分のストレスを発散させたのか、そこまでの聞き取りや分析というのはどのようになっているでしょうか。
◎加藤英二 子育て支援課長 お答えさせていただきます。
当該保育士につきましても、ヒアリングは実施をしているところでございます。その際には、今ご質問のような観点ではなく、区に提供された情報の確認、あるいは任意に提出していただきましたビデオ映像から区が確認したことについてのその辺の事実確認を中心に行ったところでございます。当該保育士について、現在休職中でございまして、行っていないところでございます。区としましても今ご質問の観点でのヒアリングは必須と考えてございます。体調を考慮しながら近い時期に実施したいというふうに考えているところでございます。
◆間宮由美 委員 そういう観点は必須であると思うと、今お答えがあったのでぜひそこのところは確認をしていただきたいと思っています。そこの分析をすることで、次に同じことを繰り返さないということにつながると思いますので、ぜひお願いしたいと思っています。
もう一つは、今回2度目ということであります。改善をしていたということがあったというふうに区は捉えていたけれども、実は2度目であったと。ということは1度目からの2年間の間ずっとそれが行われていたのか。また1回目があって2回目があって、間がなくあったのかというところもとても疑問にも思うところなのです。多分、思うに1回目があって指導はあったけれども不適切な保育というのは、ところどころでずっと続けられていたのではないかと考えられるかなとも思うのですけれども、私はそういった、大人同士とかではないので、やはり子どもに対してでありますから、そういう人をずっと子どものそばに置いておくということは、それで本当にいいのだろうかと疑問を持つのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
◎加藤英二 子育て支援課長 本区としましては、今回、2回目ということで重く受け止めているところでございます。特に、今回指導改善の中で、不適切な対応した保育士に対する指導教育を徹底し、改善を図られるまで、担任から外すなどの個別的な対応を行うことということで実施を求めているところでございます。また現在、来月4月に新年度の体制がもうそろそろ決まる頃ではないかなと思っていますので、そういったところ体制がどうなるのかも見ていきたいなというふうに思ってございます。また、園側に対しましては、先週の金曜日に私も保育園のほうに行きまして、施設長とお話をしてきましたが、保護者でいろいろな様々な意見が出ているところでございます。区がこういうふうにしてくださいとかでやるのではなくて、どうしたらこの園がよくなるのかということを、自ら考えて行動してくださいという形でお願いしてございました。また、保護者会とか今回の新入園児向けの説明会においても、保護者の方から今ご質問のようなこととかいろいろな様々なご意見を出されたところでございます。そういったことを施設長として受け止めてどのようにしたらいいかということを、今月中に考えて、体制を整えてくださいということを指導したところでございます。
◆間宮由美 委員 私は、その保育士に対する指導というのはもちろんだと思うのです。ただ、1回目があって、そして2回目になるまでのこの2年間の間、園の中で、そんなことしては駄目だよということが言われてなかったのかなというのがものすごく残念だなと思うのです。今回はようやくそれが明らかになったのは内部からのお話があったのかもしれませんが、私はこの2年間の間お互いにもっとこうしたらいいのではないか、もっとこれでは駄目ではないかとかいうことをお互いに話せない園であったのだと思うのです。でも、そうすると、今でも課長がおっしゃったように園として自ら考えてほしい、考えて行動してほしいと指導もされたということですので、そこのところをどういうふうに受け止めてどういうふうに園長先生はじめ皆さんが、1人1人の保育士さん全て含めてだと私は思うのです。言いづらいって確かにあると思います。でも、言わないと、ことは子どもですから、相手が。だから、そこに対して、園長先生はじめ皆さんが区の指導に対してどのように受け止めて、どのように今後していくかということについてはしっかりと回答も受け取っていただきながら指導していただきたいというふうに思っております。
最後になりますが、説明会などが行われた後に転園の希望はどれぐらいあって、どれぐらいの方の希望がかなえられているでしょうか。
◎木村秋生 保育課長 4月からの入園予定の新入園児家庭は8世帯でありますが、転園の希望を伺いながら、個別に対応をさせていただいております。また、在園児の家庭につきましても、ご相談を受けさせていただいております。数的なところがまだ検討中のご家庭が多いため、お答えはできませんが、引き続き丁寧に対応していきたいと思っております。
◆間宮由美 委員 既にもう2月でしたかね、転園された方もいるということも聞いています。転園というのも本当に保育園入ること自体がまだまだ大変な中で、転園をするということを決めることも大変だと思います。ぜひ丁寧に相談に乗ってあげていただければと思います。
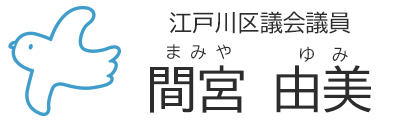
13件のコメント