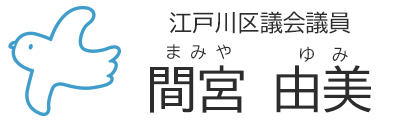| 会議 | 令和7年 6月 福祉健康委員会-06月17日-02号 |
|---|---|
| 日付 | 令和7年6月17日(火) |
| 開会 | 午前10時00分 |
| 閉会 | 午後3時17分 |
| 場所 | 第4委員会室 |
| 案件 | 1 座席の指定 2 執行部職員紹介 3 議案審査 第50号、第58号~第64号、第67号、第68号、第70号、 第71号…可決(全会一致) 第65号…可決(7:1) 第66号、第69号…可決(6:2) 第50号議案 令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第58号議案 江戸川区立くすのきカルチヤーセンター条例の一部を改正する条例 第59号議案 江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例 第60号議案 江戸川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 第61号議案 江戸川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第62号議案 江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第63号議案 江戸川区保育認定子どもの利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例 第64号議案 江戸川区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第65号議案 江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第66号議案 江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例 第67号議案 江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 第68号議案 江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例 第69号議案 江戸川区民間賃貸住宅家賃等助成条例の一部を改正する条例 第70号議案 江戸川区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 第71号議案 江戸川区住まいの改造助成条例の一部を改正する条例 4 発議案審査 第5号・第6号…継続 第5号:江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第6号:江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例 5 陳情審査 第49号の3・第51号・第53号・第65号…継続 第37号…継続に至らず審査未了 第37号:接種台帳の保存期間延長に関する陳情 第49号の3:区政等に関する陳情 第51号:マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情 第53号:自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情 第65号:江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情 第71号:電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情 第72号:「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情 第75号の2:『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情 第78号の2:魅力的な江戸川区にするための陳情 6 所管事務調査…継続 7 執行部報告 (1)令和7年度介護保険料額決定通知書等の発送について (2)公開シンポジウム「子育て×発達応援フェア」について (3)内部公益通報(令和6年度公益通報第一号)に係る報告について (4)がん患者アピアランスケア支援事業の助成拡充について (5)コロナ定期接種における有効期限を過ぎた製剤の使用について (6)国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書等の一斉交付について 8 その他 |
【協議会にして視察について】
◆間宮由美 委員 先ほど、委員長のほうから、委員会終了後に協議会にして視察についてお話をいたしますということでございました。前回の委員会の中では詳しく23区の各区の様子、視察の在り方などについて意見を述べさせていただいたところです。それを今、繰り返しはいたしません。ただ、委員会の中でこそ視察の件についてはお話をしていただきたいというふうに思っております。改めて意見として申し上げさせていただきたいと思っております。
皆さんにお諮りいただけるのであれば、ぜひそうしていただきたいと思うところでございます。
—
【第3款地域支援事業費を審査について】
◆間宮由美 委員 これは質を担保しなければならないということで、介護保険課として考えて、主任ケアマネになってからではあるけれども、ケアマネ協会さんに委託をするための費用をこのたび補正予算として上げられたということだと思います。
江戸川区では、主任ケアマネになるのはとても厳しい、ケアプラン点検が厳しいという声が幾つも出ていたとお聞きしています。また、確かに私もそのような声をお聞きしていました。しかし、今回の東京都の改正を受けまして、主任ケアマネさんたちの声を改めてお聞きしましたところ、役所は制度で話してくるので現場のことを分かっていないのにと思ったこともあると。しかし、日々現場で忙しくしていることで忘れてはいけないこと、これを役所のケアプランの点検では思い出させてもらって非常に勉強になったとおっしゃる方が何人もいらっしゃいました。
私は、江戸川区の中で3人の方が全員を見てケアプランの点検をしていてくださったわけですから、基準もはっきりしていたということにもなると思います。今度は、これをケアマネ協会さんに委託をしてケアプランを見ていただくことになるわけですが、そうしますと基準はまちまちになりはしないだろうか。あるいはケアマネ協会さん自身が現場の方たちなので、役所が見ていてくれたように、現場の自分たちが気がつかない制度面での指摘、これをしてもらうことができるだろうか。そういった疑問の声もお聞きをしたところです。
このような声があることを介護保険課としてはどのように捉えますでしょうか。そして、掛け声だけではなくて、本当に質の担保をするというためには、ケアプランの点検業務を受けてくださるケアマネ協会さんと話し合って、これまで区が行ってきた点検のポイント、蓄積があると思いますので、そのことをしっかりとお伝えいただくことが求められるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
◎山野辺健 介護保険課長 よろしくお願いいたします。
今の委員のお話ですね、区のほうとしてはケアマネジャーからすると厳しいという話をよく聞いておりまして、何とかしてほしいというような声というものをよく聞いておりましたので、今のいただいた話というのは大変ありがたい話でございましたので、まず職員のほうにも伝えさせていただければと思います。
それを踏まえまして、制度につきましては、やはり細かい部分で日々変わっていきますので、その周知、浸透、理解というものが必要になってくると。その上でケアマネ同士のケアプラン点検というのがこれで初めて生きてくるのかなというふうに考えているところでございます。この点につきましては、ケアマネのさらなる質の向上にもつながっていきますので、委員のほうでもご提案あったこと、職員のほうの知識をいかにどう伝えていくか、そういったことも考えながら検討していきたいというふうに考えているところでございます。
◆間宮由美 委員 東京都が今後見るということで、今まで区が見ていたケアプラン点検をして、その上で東京都のほうに上げて、そして推薦をするという形で主任ケアマネになっていたものが、それがなくなってしまうというところで、区としても質の担保ということを十分お考えだと思います。ですので、東京都でもう決まった後ではあるけれども、ケアプラン点検について、区としても改めて行うのだというふうにおっしゃっているところは非常に大事なことだと思っております。
厳しい厳しいと言われてきたけれども、しかし3人の方が見ていてくださったケアプラン点検、これは江戸川区の主任ケアマネさんの力量を高めることにつながっていったことであったのだということを、私は改めて実感をして感謝もしたいと思っております。
また、東京都がいきなりとも言える速度でこのように主任ケアマネになる方法を変えていったということには疑問はあるものの、変わってしまった以上進めなければなりませんので、質を担保するということについて、介護保険課として考えてくださった今回の補正予算については賛成をいたします。
—
【第59号議案、江戸川区立障害者就労支援センター条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 就労選択支援などのサービスが始まるということになると思います。
現在就労に通っている方たち、また現在高校生の方たちについては、在学中から選択できるようにするとのことですけれども、具体的にはどのような形での選択になりますでしょうか。
◎上坂かおり 障害者福祉課長 よろしくお願いいたします。
就労選択支援につきましては、こちら国の取組みで今年の10月から開始する事業です。区の就労支援センターでも実施させていただくということでの提案でございます。
具体的には、一般就労か就労継続支援AかBかというところを選択するための支援というような制度になっております。
今年度につきましては法律施行後3年生及び2年生について実施をさせていただくのですが、主に特別支援学校の在学児の生徒から実施をさせていただきます。こちらにつきまして実施する形としましては、就労を希望する方に1か月かけて就労に向けた各種ツールを使ったテストであるとか、あとは就労の場での集団アセスメント、あと学校での様子、そして大切なのが本人の意向。ここを聞いた上で、本人の強みとか弱みをご本人及び家族に伝えさせていただいて選択肢を伝えた上で、その後、一般就労か就労継続支援A型かB型かという判断する選択肢を提供するというような事業になっております。
今後3年後をめどに、今現在、就労移行を利用している方とかA型を利用している方、こういった方たちにもこの就労選択支援事業というのを適用していくというようなことで制度的にはなっております。
◆間宮由美 委員 承知いたしました。能力に合った形で働くことは、その人の人生を豊かにしてくれるものになります。賛同いたします。
—
【第60号議案、江戸川区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 実際のところ、江戸川区でのインクルーシブ保育の状況は数としては現状はないということで今ほどもお話がありました。このたび認証保育所とも児童発達支援事業所とのインクルーシブ保育が可能となるというわけですけれども、同じ施設で保育療育を行うという意義については大変よく分かるところですが、これまでもなかったということで、実際に江戸川区でこれを進めていく場合の課題、これは何になるでしょうか。
◎上坂かおり 障害者福祉課長 こちら課題についてでございますが、やはり併設ということで療育を希望する児童というのがその園の中で非常に大きくなるかなということで想定しております。そうしますと、やはり保育園の保育士のスキルというのが求められてくるというのが1点目であると思います。
あとは、療育での支援の方向性と保育での支援の方向性というのが同じでないと、児童が非常に混乱するかなというところも想定しております。
保護者目線でいきますと、療育に関する事業所があるということで、そういった子が多いのではないかと考える保護者さんが当該園を避けるといったようなことも課題としてはあるかなと考えていますが、ただ、発達に課題のある子が過ごしやすい場所というのは、当然、ほかの子にとっても過ごしやすい場所になるということで私たちは考えていますので、そういった意味での今後の幼少期のインクルーシブな関わりが子どもの将来に大きく影響を与えるということを考える中でも、今後区としても積極的にこちらは推進して応援していきたいというところで考えています。
◆間宮由美 委員 そうしますと、なぜ今まではそういう保育園が出てきていないということでしょうか。
◎上坂かおり 障害者福祉課長 法律な制度としましては、やはり中に児童発達支援などの支援事業所がつくれないというのがあったと思いますし、あとはやはり専門的な知識というのが非常に療育の中では求められるというところがございますので、そういった支援を取得するというところが難しいところだったのではないかと考えています。
◆間宮由美 委員 そうしますと、場所的なことであったり専門的知識を求められるということでそこら辺が難しいということであったとしたならば、制度はつくられるのだけれども、具体的にこう踏み出していくというところでは、まだまだ課題があるのかなというふうにも思います。
ただ、このインクルーシブを進めていこうということは、障害を持った子も一緒にいて当たり前、一緒に暮らしていると一緒にいて当たり前になっていきますので、これは進めていくことだと思いますので、先ほどの課題の部分というのを乗り越えていけるようになるといいなと思っております。
賛成をいたします。
—
【第65号議案、江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について】
◆間宮由美 委員 子どもの育ちを応援するということで、こども誰でも通園制度が始まります。先ほど課長がお話しされましたように、園に関わることになってからは、様々の親御さんもつながることができる人とか場所が持てるようになると思います。
しかし、それまでのちょうど今が隙間のような、赤ちゃんができてから園などにつながるまでの間というのは、若干隙間のような状態であったと思うのです。そこに誰でも通園制度ができたということは、これは非常に大事なことだと思っています。この施策を進めるために進めておられることについては先ほどもお話がありました。
ただ、この通園ができるようにするためには、幾つかのまだまだハードルがあると思うのです。どのような困難があるでしょうか。また子育てひろばでも一時保育ということであればしていただいていますが、今回の新たに行われるこの事業との違い、これもお聞かせいただければと思います。
◎佐藤英 子育て支援課長 はじめに、子育てひろばで行われている一時保育との違いですが、ひろばの一時預かりは保護者の負担軽減を図ることを目的としていることに対しまして、誰でも通園制度については子どもの成長の支援を目的としております。
◎森澤昌代 保育課長 続きまして、ハードル、困難があるということで幾つか課題をご説明させていただきたいと思います。
本区では、ここ数年待機児童ゼロを堅持しておりますが、保育園の空き状況につきましては必ずしも余裕があるとは言い切れません。本来の保育園入園希望者への需要に対応しつつ、こども誰でも通園制度への利用者を受け入れる体制を現在検討しているところでございます。
現場からの声といたしまして、ゼロから2歳という低年齢児童をお預かりするという点で、親子分離に対して不安を感じる場合もあると想定しております。お子様が環境に慣れるまでの時間には個人差があり、楽しんで通園できるようになるまで保護者の方と信頼関係の構築が必要ですので、先ほども同じことの繰り返しになりますけれども、慣れるまでは親子通園を可能にするなど、親子で安心できる取組みを進めていきたいと思っております。
また、食事に関しまして、離乳食の進み具合やアレルギー、宗教食などへの対応など、一人ひとりへの細やかな配慮が必要となっております。在園しているお子さんとこの制度を利用されるお子さんとの活動のバランスにも配慮が必要でございます。
このような丁寧な受入れや対応を行い、安全で安心できる環境の提供には、人的、物的環境の整備は重要と考えております。
◆間宮由美 委員 これまで子育てひろばでは保護者の支援が主で、この誰でも通園制度は子どもの支援を目的にということだと思いますが、きっとどちらも、やはり保護者も子どもも両方とも支援していくという目的に変わっていっていいのではないかなというふうに私は思っております。
現在、制度自体は非常によいこととは思うものの、実際には既に空きがない状態の施設について、どのように誰でも通園を可能にするかということはこれからの具体的な設計にかかっているのだと思います。各園、各関係者とお話をしっかりと詰めていただきながら、床面積ですとか人員配置ですとか、子どもたちにとってよりよい方向になるようにということで、難しいことがまだまだあるようですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
—
【第66号議案、江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 現在受けている方々については、そのままこの制度の中でやっていくと。それで、新規の方からこの額、また40歳以上ということの見直しの案については適用されるということとお聞きしています。そうであれば、年額は若干下がるわけなのですけれども、全体を見る中でこの減額については反対をするものではありません。
ただ心配は、要介護4以上で介護サービスを受けていない家庭というのは、介護拒否とか、あるいはネグレクトなども考えられると思います。区としては、こういったネグレクトや虐待を事前に見つける、あるいはそれらの防止のために定期的なご報告も義務づけるというふうにおっしゃっているわけなのですけれども、しかし、実際のところ10万円をもらう、もらってからそこから介護につなげようとしたときに、いや10万円がなくなってしまうから介護は受けさせないという人が出てくる可能性があるのではないかなという、そこが心配されるところです。そこについてはいかが考えますでしょうか。また、受給者が本人から介護者に変更になるわけですが、単身世帯の場合はどのように考えることになるでしょうか。また今回の受給される方は、見直し案として受給される方ですね。これは何人くらいと想定されているでしょうか。三つお聞かせください。
◎山野辺健 介護保険課長 まず、ネグレクト防止についてでございます。今も介護サービス拒否者支援という事業を実施をさせていただいているのですけれども、これ何らかの理由で介護サービスが途絶えてしまった場合に、ケアマネジャーと熟年相談室で連携をして、本人や家族を説得して再度適切に介護サービスを利用していただくようこういった対応をしているところでございます。これと同様に、介護サービス利用が必要な場合については積極的に勧める形を取っていきたいというふうに考えているところでございます。
ただ、それでも介護サービスの利用の拒否があって、かつ適切に介護されていないというふうに判断ができる場合につきましては、ネグレクトとして虐待対応として当たるということも考えているところでございます。そういった意味では、ネグレクト防止、虐待の早期発見ができるものというふうに考えているところでございます。
それから、単身世帯についてなのですけれども、今回は家族介護支援が目的でございますので、対象とはいたしておりません。ただ、単身の方で要介護4、5の方でサービスを利用していない方というのは、今現在システムで確認をしたところ、現在対象の方がいないというふうに判断をしているところでございます。実際、他区でもこの事業の対象者少なくて、本区で実施した場合も同様というふうに考えておりまして、ただ、もちろん要介護4、5の方で今後単身の方でサービスを使っていない方があれば、本事業に関係なく、それは熟年相談室ですとかそういったところで対応していくというふうな必要があるというふうに考えているところでございます。
それから、本区でどのぐらい人数がいるかというところなのですけれども、他区の状況から見て、それから要介護の認定者の状況から見て、大体年間10人程度というふうに考えているところでございます。
○中道貴 委員長 よろしいですか。
◆間宮由美 委員 これまでもケアマネさんと熟年相談室さんでお話しして対応してくださってきているというのも存じております。今回改めてそういう方が分かった場合には、ネグレクトとしての虐待対応ということにも切り替えるということですので、そこはきっぱりとお考えいただいているので、非常に大事なところだなとは思っています。
それから、単身世帯の場合ですけれども、今はいらっしゃらないという、単身世帯で要介護4以上で、そして介護を受けてない人がいないということですけれども、セルフネグレクトということもかなり問題になっております。今後出てくる場合というのはあると思いますので、そのときにはお金を渡すとかいうことではなくて、しっかりと介護につなげていくという方向でお考えいただいているということですので、そこのところはよろしくお願いしたいと思います。人数的には10人ぐらいということで非常に少ないのだなというのは分かりました。
なかなかやはり一番は、介護をしている人が介護を受けさせない、10万円もらったからもうより受けさせたくないという、そういうふうになってしまうことがやはり心配なのですけれども、難しい面はあるとは思いますが、しかし、高齢者の尊厳を守るために、制度としても必要であれば改定ということも繰り返すことも含めて、今後ともお考えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
—
【第69号議案、江戸川区民間賃貸住宅家賃等助成条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 これは、もともと今住んでいたところが老朽化して建て替えますよといったときに、例えば5万5,000円だったらば、もう5万5,000円のところがなくて6万円のところになる、じゃああと5,000円の差額分を区が出しますよということでずっと行われてきて、私は江戸川区でこの制度を知って、本当にありがたいなということはずっと思っていました。
このたびの見直しの中では、高齢者についてはそれが75歳以上の方ということで、亡くなるまでこれは出る、でも75歳以上からという期限がある。ひとり親に限っては、子どもが18歳になるまでという期限がある。障害者の方はずっと何十年であっても亡くなるまでということだったものを、ほかとも合わせながら障害者にも一応の区切りをつけようということで、この10年ということが長いか短いかといったらば、もちろん長くしてもらえば、それはそれでこしたことはないのですけれども、どこかで切るといったときに、今回都住の申込みとの関係で考えたということで、先ほどのご説明もあっていました。
都営住宅、これまでは確かに入れなかったわけなのですけれども、今も本当に入れないという方はまだまだいらっしゃいます。ただ、人数が減っていく中で、10年の倍率の10倍、10年での都住にも転居もできるかもしれないということも含めてのことであるということなので、今までとはまた違う状況はあるのかなというふうに思います。ほかの高齢者、ひとり親との関係でどこかで期限を切らなければならないということで、これについては反対をするものではありませんと考えました。
—
【第71号議案、江戸川区住まいの改造助成条例の一部を改正する条例について】
◆間宮由美 委員 全体のつくりの改定については反対をするものではございません。
お聞きしておきたいことは2点です。負担割合が変わる人たちはどのような割合であるかお示しください。
また、このたびホームエレベーター、流し、洗面台が新規で加わることになりました。その理由についてお聞かせください。
◎山野辺健 介護保険課長 負担割合の変動についてなのですけれども、過去の実績から推計いたしました。非課税世帯の方は負担割合なしから1割負担になるので、そういった方は全体の3割強いらっしゃいます。それから、今まで2割負担だった方が、逆に1割負担になる方、こういった方は全体の2割弱ということになります。今回、介護保険の負担割合に合わせるということで新たに3割負担の方いらっしゃいますけれども、そういった方は、年間の中でも大体数件程度だったということでございます。ですので、それ以外の方につきましては、今までと負担割合が変化なしということになりまして、約半数の方がそういった方に該当いたしまして、多くの方は1割負担だということで考えております。
それから、もう一点、あと、洗面台とホームエレベーターの新設した理由でございますけれども、こちら都の補助事業でのメニューの一つになっておりまして、本人負担を差し引いて、基本的には都と区が2分の1ずつ補助する形で事業が実施できるということから、追加をさせていただいたというところでございます。
◆間宮由美 委員 若干上がる方がいるので、ここのところは非常にいかんともし難いのですが、しかし、介護保険と同じにするということ、負担割合と同じにするということは、逆に分かりやすいというか、すっきりするのではないかというふうには思ってはいます。
住まいの改造助成があるということで、どんなに助かったかという声をたくさんお聞きしています。実際の場面で新たに加わった流しとか洗面台、こういったものは日常生活に不可欠なものですので、自立のためのものとして加わったということで、これについては賛同いたします。
—
【第37号、接種台帳の保存期間延長に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 予防接種に関する議論がされている厚生科学審議会では、接種台帳の保存期間についての延長の方向の案が出ているというところまで確認ができていますが、その後、厚生科学審議会での話はどのようになっていますでしょうか。
◎飯嶋智広 健康部参事 その後の厚生科学審議会についてですけれども、この件につきましては、令和7年1月9日の福祉健康委員会のほうでお話しさせていただいたところでございますが、1月29日に行われました第60回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の中で、参考資料として予防接種基本計画改定のポイントという点で述べられております。この内容につきましては、第63回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で話し合われた内容と同じでして、この部会につきましては、令和6年10月10日に行われたものと同じでございます。
内容といたしましては、中期的な視点での施策と基本計画の記載の方向性ということで、予防接種のデジタル化の着実な推進ということが述べられておりまして、過去の接種記録が生涯にわたり、接種可否の判断等に影響を与える可能性もあることも踏まえ、接種記録の保存年限を延長するということが述べられておりますが、これにつきましてはさきに述べられたものと同じということですので、特に変わった進展というものはございません。
◆間宮由美 委員 承知いたしました。保存年限については延長の方向という話は出ているということが改めて確認ができました。これについては国もそのように言っているということ、そして私たち自身も、年限を延ばすということについては賛同できるものと思いますので、今回、結論を出す方向で取り仕切りをお願いしたいと思います。
◆間宮由美 委員 確認ですが、本日出さないと、もう間に合わないのですね。ということは、そのことを分かった上でここに臨むことが必要だったのではないかなと、やはり申し訳ないけれども、思います。
なので、本日どうしても持ち帰らないと駄目だということであれば、仕方がないとは思うのですけれども、残念であると思いました。
—
【第49号の3、区制等に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 この陳情に書かれている願意については、既に江戸川区内で対応がされていることも、これまでの委員会の中のお話の中でも分かっていることであります。ですから、これは結論に向けた話合いとして進めていただければと思うところでございます。
—
【第51号、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 陳情の願意であるのは、現行保険証とマイナ保険証との両立、これを国に意見書として出してほしいということなわけですが、現在のところ、健康保険証とマイナ保険証、これは両立ができているということで、陳情の願意はおおむね達成できているという方向であるということが、この間委員会の中でも話し合われてきたことかと思われます。
また、更新などについても、区としては丁寧に進めていただいているということもお聞きをしてまいりました。
ただ、審議がまだ続いておりますので、現状についてお聞きをしたいと思います。マイナ保険証については様々報道がされているところなのですけれども、区としての改めて問題点、課題と思うところをお聞きをしたいと思っています。
さらに、ひもづけの解除件数が多くなっているという報道もなされているわけですけれども、区としての解除の件数、そして新たな登録件数をお聞かせいただければと思います。
◎加藤広司 医療保険年金課長 まず、江戸川区における国民健康保険証のマイナ保険証登録件数について申し上げますと、6月2日現在で、6万2,159人となります。全体の被保険者数の55.81%となります。
また、解除登録申請の件数につきましては、月に大体平均で30件程度となっておるところです。
一方、12月2日から見ますと、月平均680件ほど新規に登録され、徐々にではありますが、毎月少しずつ登録率というものは伸びているということでございます。
次に、課題ということでございますが、やはり課題と申し上げますと、マイナ保険証の普及がまだ十分ではないというふうに考えられることであると思います。これはマイナ保険証を使えば、高額な医療費がかかった場合でも、事前に手続をすることなく医療機関等窓口でマイナ保険証を提示するだけで、高額療養費の限度額までしか自己負担を支払う必要がないというメリットがあります。
一方、資格確認書を使う場合には、同様な支払いとするには、事前に区役所で手続をする必要が出てきます。このほかにもメリットはございますが、高額療養費の件は大きな利点であると思います。
このようなメリットを多くの人に利用してもらうためには、マイナ保険証の普及が必要になると考えます。なので、現時点では、その普及が十分とは言えるわけではございませんので、これが私たちの課題だというふうに思っております。
しかし、強制的に保有させるという制度設計ではございませんので、今後も徐々に浸透していくものと考え、推移を見守りたいと考えております。
◆間宮由美 委員 解除をする方々が毎月大体30件程度。新たに登録をされる方が毎月680件程度ということで、非常に多くなっているのだと思います。
最後にお聞きしておきたいことは、解除された方の理由、また新たに登録された方の理由はそれぞれお分かりでしょうか。もしお分かりでなければ、ぜひ次回に、このことについてはお聞かせいただきたいと思うところでございます。
—
【第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について】
◆間宮由美 委員 今ご報告があった署名の数なのですけれども、800から200ということで無効なものがあったということですが、具体的には無効というのはどういうものなのでしょうか。
◎区議会事務局 署名欄につきましては、必ず陳情文と同じ様式に設けるということで、ホームページのほうでも周知をしているところなのですけれども、今回のケースですと、陳情文の書面のほうに陳情文が載っておらず、署名のみの署名簿というものが含まれておりましたので、こちらは無効となります。
◆間宮由美 委員 一般の方々がこうして意見を通そうとしながら考えられたんでしょうけれども、残念でしたね。
子育てひろばは、いかに大事な事業であるかということは、私自身もまた毎日ご相談をお受けしている身としても実感をするところです。
民間の子育てひろばにつきましては、1か所1団体の方々が15年もの間担ってくださっているということで、要綱では上限750万という補助金ですけれども、これが出ていますが、それは15年間変わっていないということでよろしいでしょうか、これが一つ目です。
またもう一つは、こども家庭庁の政策に準じた額にしてほしいということですが、それが902万3,000円、これは全国一律のものとなっていると思います。物価高騰の折、補助金を増額するということは必要になってくるのかと思うところですが、今増額されていないというところには何が課題となっているか、お聞かせください。
◎佐藤英 子育て支援課長 民間の子育てひろばについては、長年団体さんが取り組まれていることに大変敬意を表します。
補助金につきましては、区の要綱に基づき、年間の補助限度額750万円の補助金を支給させていただいているところです。国の地域子育て支援拠点事業では、常勤職員を週5日間以上配置することなどの一定の条件がありまして、現在持っている区の規定とは異なっております。
あと、15年間補助金が変わっていないかという点につきましては、当初より変わっておりません。
◆間宮由美 委員 では、条件が整えば進めることができるということだと思いますので、そういったことも陳情を出されている方々にもご説明してさしあげながら、ご一緒に進めていけるといいのではないかなと思いました。
—
【第72号、「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情について】
◆間宮由美 委員 1点お聞きをいたします。
これまで出されてきた広告の中で、このガイドラインに違反するようなものというのはありましたでしょうか。
◎新井喜代美 生活衛生課長 江戸川区の実績としましては、令和3年度にそういったチラシの違反というものがこちらのほうに通報がありまして、施術所のほうに口頭指導をしております。
◆間宮由美 委員 その1件だけあったということでございますか。
◎新井喜代美 生活衛生課長 そうでございます。
◆間宮由美 委員 それは、例えば、参考として見せていただくことができるようなものでしょうか。
◎新井喜代美 生活衛生課長 当時のそういったチラシ等は保存しておりませんので、申し訳ありませんが、提出はできません。
—
【第75号の2、「共生社会ビジョン」の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について】
◆間宮由美 委員 「中サービス-中負担」の中で提案がされて、その後にこれが書かれたのかなと思うのですけれども、しかし、区としては、その後、6月議会で改めての提案がされているところです。記書き1、2に関わることについて、区として出されている提案について、ご説明をいただけますか。
◎白木雅博 福祉推進課長 私のほうからは、1番の子ども食堂についてということでの回答になろうかと思いますが、今、間宮委員からお話しいただいたとおり、先日の第2回定例会の一般質問において、区長のほうから答弁させていただいて、今後新しい補助制度ということを検討していくという回答をさせていただいているというところでございます。
◎岡田久仁子 健康推進課長 私のほうからは、健康診断の一部有料化を中止してくださいということに関しまして、健・検診に一部自己負担の導入を検討するということに関しての今後の方向性ですが、持続可能な健・検診事業とするために、一部自己負担の導入については、関係団体の皆様と協議を継続いたしまして、その上で、導入対象とする健診、自己負担額の設定、低所得者への対応などについても協議をするとともに、さらなる受診率向上への取組みについても検討していく方向性となっております。
◆間宮由美 委員 たくさんの意見を受けて、区としてもまた方向の転換や、あるいはさらに進めるという形になっているかと思います。特に健診の自己負担の方向については、関係団体と話合いを継続しながらということですが、今後のどういうふうに話合いをされていくのかということ、いつ頃に決定をする予定であるかということをお聞きしたいと思います。
また、子ども食堂についても、補助金は削減はしない方向、条件付きではあるけれども、継続する方向というふうに舵を切られたと本会議でも示されたと私は思っております。今後このことをどのように関係者にお示しになるのかということをお聞かせください。
◎岡田久仁子 健康推進課長 健診につきましては、医師会、歯科医師会の先生方には、方向性が決まった時点でご報告をさせていただいております。それを踏まえて、今後どのような形で検討をしていくかということは、今後の協議となっております。今はその時点でございます。今後いつの時点でということも踏まえまして、今後の検討内容に合わせていくことになります。
◎白木雅博 福祉推進課長 子ども食堂につきましては、今回、定例会でお答えさせていただいて、方向性をまずはネットワークに加入されている子ども食堂の方々にお知らせさせていただいた上で、今後どういう形で運営をしていくのか、補助制度をつくっていくのかを、具体的に各食堂の方々と意見交換をさせていただく場を設けて協議をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
◆間宮由美 委員 健診の自己負担につきましては、今後どういうふうに進めるかも含めて、医師会、歯科医師会の先生方ともお話合いをこれから進めるということですので、どのように進んでいくかなど決まりましたらば、またご報告いただきたいと思います。
子ども食堂につきましては、またこれも関係者の方々と意見交換をするということなのですけれども、削減はしないという方向の舵を切ったということは、まず先にお知らせをしていただきたいと思います。既にこれは動いていることですので、どのように工面をしていくかということで皆さん大変心配されていますので、そこについてはお知らせいただきたいと思います。そういうことをお聞きしながら、陳情については今後また検討していきたいと思います。
—
【執行部報告:児童相談所について】
◆間宮由美 委員 今の児童相談所の件につきましては、援助課長からも、また児童相談所の所長からも、職員間のコミュニティ不足だけでなくて、お互いのリスペクトがなかったということでお話がありました。私はそういったことをきちんとどこが課題だったのかな、問題だったのかなということで突き詰めて考えてくださろうとしていることに、本当に信頼が持てると思ってお聞きをしました。
お聞きをしたいほうは、ウィッグ等の購入レンタル費用のほうになります。若い方でもがんになる方が非常に増えている中で、ウィッグ等の購入のお金が出るといいなといってお亡くなりになってしまった方なども存じております。でも、ウィッグ自体はとても暑くて頭の中が蒸れてしまうと、よくつけている人たちもおっしゃっていることもあるのです。かなり改良はされてきているものの、やはり具合が悪いときにずっとつけているというのは難しいので、帽子、特に通気性のいいものとか綿のものとか、そういったものを日常的にはつけて過ごすという方も多いのですけれども、そういうのだと1,000円とか2,000円とかで買えるものなのです。ここには毛つき帽子とか医療用帽子と書いてあるのですけれども、そういった簡単なものなんかもここの中に対象品として入ってくるということでよろしいでしょうか。
◎岡田久仁子 健康推進課長 今、間宮委員がおっしゃったように、外出ではなくて、室内でも外でもずっとつけていられるような帽子が、医療用帽子として結構販売されております。なので、そういうものも対象になってきます。
◆間宮由美 委員 1件につき複数点の補整具を含めることが可能だけれども、1人につき2件までとあります。先ほど言ったような安いものであれば、医療用帽子という1件というくくりで見ていただいて、高いものも含めてというふうに換算していただけるときっといいのかなと思います。
しかし、こうやってまたさらに助成対象品も増えているので、本当に喜んでいる方がたくさんいます。ありがとうございます。
—
【臨海病院における小児科での緊急搬送の受入れについて】
◆間宮由美 委員 臨海病院における小児科での緊急搬送の受入れについてです。
この半年の間で2回救急搬送された乳幼児のお母さんから、近くに臨海病院があるのだけれども、そこには救急搬送はできないと言われて、先週は昭和大学の江東豊洲病院に行った。今年1月のときには、順天堂大学の浦安病院に搬送されたということなのですね。お子さんが2人いて、2人ともお体が弱いから不安であるということで、近くの区内の臨海病院で受入れと入院までできるとありがたいということをお話しされていました。実はこのお母さんだけでなくて、このような声が幾つも聞かれるようになりましたので、今回、委員会の中でもお聞きしようと思った次第なのです。
臨海病院のホームページを見ますと、医師の異動等のために、令和6年4月から診療体制縮小を余儀なくされていたけれども、新たな体制に向けて整備しているということが書かれています。また、救急ということについては、小児科医師が当直している日のみ限定だけれども、夜間の小児救急患者受入れを再開予定ですとありました。小児科医が少なくなっているというのは全国的な問題でもあると思いますが、実際のところの臨海病院についての体制について、また、区内での小児科の状況について救急対応ができるのか、診察はできるのか、入院はできるのか、お聞きしたいと思っております。これはただ、今回もう長くなっていますので、次回で結構ですので、区内小児科の状況についてお聞かせをいただければと思っている次第です。